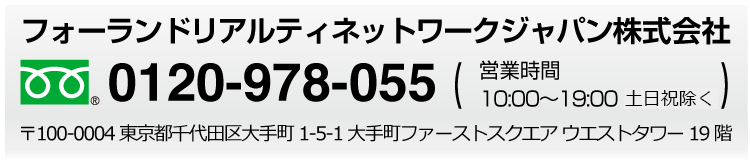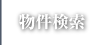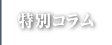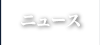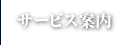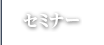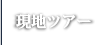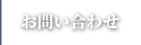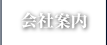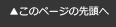海外不動産の投資・購入・売却、セミナー、物件視察ツアー、海外移住はフォーランドリアルティネットワークへ
特別コラム&記事
特別コラム&記事(詳細)
2025.02.12
【コラム】真逆の日米金融政策で円高進む?日本円を取り巻く環境を再確認

日本銀行は2025年1月末の金融政策決定会合で、政策金利を0.25ポイント引き上げ0.50%とすることを決めました。2024年3月の会合で17年ぶりの利上げに踏み切って以降、計3回目の利上げとなります。
一部の日銀審議委員から年内に1~2回の追加利上げを行う可能性がすでに示唆されているなど、金融政策の正常化を進めたい日銀の意思が明確になってきています。
一方、米連邦準備制度理事会(FRB)は昨年9月に利下げに転換。政策金利に当たるFF金利(フェデラルファンド・レート)の誘導目標は、ピークの5.25~5.50%から現在は4.25~4.50%まで低下してきています。
米連邦公開市場委員会(FOMC)参加者の金利予想をまとめた通称「ドットチャート」の最新データを見てみると、2025年末時点のFFレート誘導目標の予想中央値は3.875%となっており、年内にあと2回程度の利下げが見込まれています。
このように、昨年から日米で真逆の金融政策が進められている状況にあるわけですが、メディアなどが「FRBが利下げすれば円高になる」「日銀が利上げすれば円高になる」と喧伝していたのに反して、ドル円相場は執筆時点でも依然として1ドル=150円台をキープしています。
もちろん、ドル円相場は一時160円台を付けましたから、それよりは円高になったと捉えることはできますが、コロナ禍前は100~110円程度だったことを考えると、日本の円安構造は思いのほか根深いものなのかもしれません。
そこで今回は、日本円を取り巻く環境をいくつかのキーワードに分けて整理し、理解を深めていきたいと思います。

ドル円の長期チャート
【キーワード1】日米金利差
日米の金利差は、短期的に為替相場との関連性が高い要因として知られています。日米の金融政策の転換によって、足元の日米金利差は政策金利ベースで4%程度(ピークは5%超)、10年債利回りベースでも3%程度(同4%超)まで縮小してきています。
とはいえ、日米金利差は過去に照らして依然として高水準にありますし、日本の政策金利自体も物価を加味した実質金利ベースで見ればマイナス1.5%程度と緩和的な水準にとどまっています。こうした点が、しぶとい円安圧力の一因になっていることは間違いないでしょう。

日米の10年債利回り差
今後、日銀の利上げやFRBの利下げが進んでいけば、日米金利差に起因した円安圧力は一段と弱まっていくと考えられます。ただし、消費が活発なアメリカでは拙速な利下げはインフレ再燃のリスクを高めますし、まだまだ脆弱な日本経済が連続的な利上げに耐えられるのかという問題もあります。
ここからの日米の金融政策担当者は、これまで以上に難しい舵取りを迫られることになりそうです。
【キーワード2】対内直接投資・対外直接投資
「対内直接投資」とは、外国企業が日本で事業活動を行うために企業に投資したり、生産設備などに投資したりすることを指します。反対に「対外直接投資」は、日本企業が海外に対してこれらの投資行動をとることです。
投資を行う際に為替取引が発生する場合、前者は円高要因、後者は円安要因と考えることができます。
以下のグラフを見ていただくと一目瞭然ですが、近年の日本では対外直接投資の伸びが圧倒的に勝っている状況にあります。特に、東日本大震災が発生し、かつ総人口の本格的な減少も始まった2011年頃からの対外直接投資の伸びは顕著です。
さらに、通常なら円安は対内直接投資を促進し、対外直接投資を抑制する力が働くはずですが、統計を見る限りではそうした動きにはなっていなそうです。

背景には、購買力の低下、労働力確保への懸念、相対的に見て高い電力コストや税金など、日本が事業環境に様々な課題を抱える中、投資先としての優先度が下がってきていることがあるのでしょう。
もちろん、対外直接投資が増えること自体は悪いことではなく、日本企業が海外で稼ぐための足場をしっかり作っていっていると捉えることができます。ただ、海外拠点での利益の大部分はそのまま現地で再投資されることが多いため、結果として日本円には円安圧力がかかりやすい状況が続いてしまっています。
これを変えるためには、日本が投資先として選ばれるための環境整備を行い、世界最大の半導体受託製造企業「TSMC」の熊本誘致のような事例を次々と生み出していく必要があるでしょう。
【キーワード3】貿易赤字
財務省によると、2024年通年の貿易収支は5兆3,325億円となり、4年連続の赤字に終わりました。日本の貿易収支は2011年以降、ほとんどの年が赤字であることを考えると、「貿易立国・日本」の姿はすでに遠い昔のものと言えるでしょう。
これだけの円安が続いているにも関わらず、日本が貿易黒字を稼ぐことができなくなってしまった背景には、まず先述の対外直接投資にも繋がるところですが、日本企業が生産拠点をどんどん海外に移転してしまったことが影響していると考えられます。いわゆる「産業の空洞化」という現象です。
現在、多くの日本の製造業が過去最高益を叩き出していますが、その大部分は海外で生産し、海外で販売をすることで実現しているものという悲しい現実があります。当然、そこで稼いだ利益の多くは現地で再投資されてしまいます。
ただ、海外生産を行う日本企業の割合はすでに70%を超えており、その水準には頭打ち感が出ているといいます。労働力の不足はネックとなりますが、今後、日本国内に生産拠点を回帰させる動きが広がれば、貿易面での資金フローは改善が期待できます。

一方、貿易黒字が稼ぎにくくなっている要因としては、電源構成の変化も見逃せないでしょう。
東日本大震災前までの日本の電源構成は原子力が26%を占め、石炭(27%)、天然ガス(28%)と並ぶ重要な位置にありました。しかし、震災以降は大部分の原子力発電所が停止・廃止となったため、現在の電源構成は原子力が6%に低下。対照的に石炭が31%、天然ガスが34%にそれぞれ拡大したことでエネルギー輸入コストが急増しており、貿易収支にマイナスの影響を与えています。
政府は、2030年までに電源構成に占める原子力の割合を2割に引き上げる目標を掲げていますが、国民感情的にも難しい問題だけに実現は難航する可能性が高そうです。
【キーワード4】デジタル赤字
近年、日本円を語るうえで、「デジタル赤字」の動向が注目されるようになってきています。
現在、多くの日本企業は、Amazonの「AWS」やMicrosoftの「Azure」といったクラウドサービスを使って事業を行っています。また、多くの日本人がiOSやAndroidが搭載されたスマートフォンを使い、NetflixやYouTubeで動画を閲覧し、InstagramやXで“いいね”を押しているでしょう。
こうした状況を反映するように、国際収支統計におけるサービス収支の中のデジタル関連支出(クラウドサービス、動画配信、ネット広告など、様々なデジタルサービスへの支出)は年々増加。2014年に約2.1兆円だったデジタル赤字は、2024年には約6.6兆円と3倍超にまで拡大しています。

特に、コロナ禍以降のDX(デジタル・トランスフォーメーション)化の流れもあって、ここ数年はその赤字額の拡大スピードが著しく加速しているのは気掛かりです。
正直なところ、この分野で日本がアメリカ企業に真っ向勝負を挑むのは現実的ではないでしょう。そのため、日本としてはデジタル赤字を穴埋めできるような新たな稼ぎ頭が必要になりますが、現在のところはまだそれを予感させるようなものは出てきていないのが苦しいところです。
【キーワード5】インバウンド観光客
日本政府観光局(JNTO)によると、2024年通年の訪日外国人旅行者数は前年比47.1%増の約3,686万人(推計)となり、過去最高を更新しています。また、財務省が発表した同年の旅行収支も5兆8,973億円の黒字と、過去最大の黒字額だった2023年の3兆6,314億円を大幅に上回りました。
こうしたいわゆる「インバウンド観光客」は、日本円を買い支えてくれている貴重な存在です。相対的なコストパフォーマンスの良さから、今後も日本旅行に対しては旺盛なニーズが続く可能性は高いでしょう。

一方で、こうした旺盛なニーズに、受け入れ側の体制がどれだけついていけるのかという問題があります。すでにホテルや飲食店では人手を確保するのが難しくなってきており、ニーズはあるのに稼働率や席数に意図的に制限をかけないといけないというケースも出始めていると聞きます。
このような供給制約は年々強まっていくことを考えると、ここから先もインバウンド観光客による円買い需要が順調に拡大していくかは不透明な部分が大きいと言えるでしょう。
【キーワード6】キャピタルフライト
「キャピタルフライト(資本逃避)」とは、政治・経済が混乱して国への信任が失われた際に、国民が資産防衛のために自国通貨建て資産の保有をやめ、より信用力のある外貨建て資産に逃避する行動を指す言葉で、発展途上国ではたびたび見られる光景です。
通常、国への信任が相対的に高い先進国ではなかなか発生せず、日本でもこれまでは潤沢な資産を持つ一部の富裕層にとどまる動きでした。しかし、足元でこうした構造は崩れ始めている可能性があります。
それが、2024年1月からスタートした「新NISA」の存在です。上限額・期間ともに旧制度より大幅に拡充され、投資家側から見ると使わない理由がない位にありがたい投資非課税制度となりましたが、それ故にこれまで投資に関心を持っていなかった一般層も巻き込んでいる状況にあります。
金融庁のデータでは、2024年末時点のNISA口座数(新旧制度の合算)は約2,560万口座と、国民の約5人に1人が口座を保有しているようです。年齢別のNISA口座保有率は30代が約32%と最も高く、旧制度時代の2019年末と比べては約3倍に拡大。20代の口座保有率も旧制度時代の約4倍、40代も約2倍となっています。
では、そんな魅力的な制度である新NISAがなぜキャピタルフライトに繋がるのかというと、その資金の多くが相対的に高いリターンが期待できるとして外国株式に投資されているからです。
金融庁によると、NISA口座を通じた2024年通年の買付額は約17兆4,485億円(2023年は約5兆6,910億円)。公式なデータはないものの、証券大手各社からの情報を総合すると、このうちの5~6割程度の資金が外国株式(投資信託含む)に向かっていると推測されます。
現状では新NISAが日本円の方向性を決定付けるような要因になるとは思いませんが、積立投資による着実な円売りフローは、じわじわとボディブローのように日本円にダメージを与える可能性があります。

まとめ
ここまで見てきたように、現在の日本円が置かれている円安環境は、利上げをすれば万事解決という単純なものではなく、かなり根深いものである可能性があります。
先日には石破政権初の日米首脳会談が開かれましたが、その成果として披露された内容には、「日本企業の対米投資を1兆ドルに引き上げ」「対日貿易赤字の削減」といったように、先行きの円安圧力を想起させるようなものが多く並んだことも、この問題を解決することの難しさを感じさせます。
とはいえ、様々な要因が複雑に絡み合う為替相場は、金融市場の中でも最も予想が難しいと言われているだけに、自身の為替予想にフルベットするような投資は得策ではありません。
弊社としては引き続き、円建て資産と外貨建て資産に50%ずつ振り向ける資産配分をベースにし、なるべく為替変動に対してニュートラルなポートフォリオを構築していくことをおすすめします。
関連記事
2024.05.10
【コラム】ドバイで不動産投資をするメリットとは?
 ※本コラムは、提携しているドバイの大手不動産仲介会社「Driven Properties(ドリブン・プロパティーズ)」から寄稿していただいた原稿を基に構成しています。
はじめに
今や中東経済の中心地となっているドバイですが、かつてはペルシャ湾で採れる天然真...[記事全文]
※本コラムは、提携しているドバイの大手不動産仲介会社「Driven Properties(ドリブン・プロパティーズ)」から寄稿していただいた原稿を基に構成しています。
はじめに
今や中東経済の中心地となっているドバイですが、かつてはペルシャ湾で採れる天然真...[記事全文]
2022.04.15
【コラム】止まらない円安、海外資産の重要性を再認識
 ルーブルよりも弱い円、20年ぶりの円安水準に
コロナ禍入りして以降、じわりと続いてきた円安ですが、ここにきて歯止めがかからない状況となってきています。年初に1ドル=115円程度だったドル円相場は、4月15日現在、一時126.50円台を付けて約20年ぶりの円安水準...[記事全文]
ルーブルよりも弱い円、20年ぶりの円安水準に
コロナ禍入りして以降、じわりと続いてきた円安ですが、ここにきて歯止めがかからない状況となってきています。年初に1ドル=115円程度だったドル円相場は、4月15日現在、一時126.50円台を付けて約20年ぶりの円安水準...[記事全文]
2018.07.09
【コラム】内藤忍氏/ アジア新興国の次にくる投資対象国はどこか?
 先月末からトルコとウクライナに行ってきました。主目的はウクライナのキエフにある不動産投資物件の視察でしたが、トランジットで2日間だけ滞在したイスタンブールにも投資の大きなチャンスがあることに気が付きました。
たまたまイスタンブールの街角で出会ったトルコ人が、私と共通の知...[記事全文]
先月末からトルコとウクライナに行ってきました。主目的はウクライナのキエフにある不動産投資物件の視察でしたが、トランジットで2日間だけ滞在したイスタンブールにも投資の大きなチャンスがあることに気が付きました。
たまたまイスタンブールの街角で出会ったトルコ人が、私と共通の知...[記事全文]
バックナンバー検索
- キーワードで検索
投稿更新日:2025年02月12日

![海外不動産情報サイト[投資・居住・別荘・投資分散]](https://www.foreland-realty.com/wp-content/themes/sp-foreland-portal/images/common/img_exam.png)